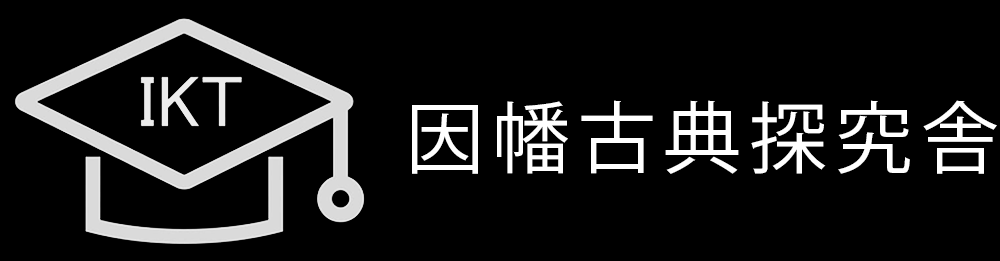「奉公十則」3ー2 公正無私を旨とし名利の心を脱却すべし
今回は、鈴木貫太郎の「奉公十則」の3番目
「公正無私を旨とし名利の心を脱却すべし」の後半部分をみていきましょう。
名利の心ってどんなこと?
「名利の心」とは、
「名誉欲」
「利益欲」
この2つの心です。これは中国古典ではなく、仏教を聞かなければ分かりません。小生は寺生まれの寺育ちでもありますので、そちらの観点からお話しましょう。
仏教では、欲と一口に言っても五つ説かれています。
名誉欲とは「誉められたい欲の心」
利益欲とは「金や儲けなどの利益を求める心」
このように言います。褒められて嬉しくなるのは、この名誉欲が満たされたからであり、利益を得て幸せを感じるのは、この利益欲が満たされたからに他なりません。これらの欲から離れ切ることは不可能でありますので、鈴木貫太郎が言うところの「脱却すべし」は、字義どおりの理解をすべきではないでしょう。
脱却とは―不淫・不移・
脱却とは―不淫・不移・不屈これなり
見出しの単語は、『孟子』の出典となるものです。原文は以下のものになります。
富貴も淫すること能はず。貧賤も移すこと能はず。威武も屈すること能はず。此れ之を大丈夫と謂ふ、と。(内野熊一郎・著『孟子』)202頁
如何なる富貴を以てしても誘惑することはできず、如何なる貧賤の苦しみを以てしても節度を捨てさせることはできず、如何なる権威や力を以てしても信念や志を曲げることはできない。これを真の「大丈夫」というのだ―
富や地位といったものに誘惑されて凋落していき、貧賤の苦しみに耐えかねて不義・不正に走りゆく。「四百四病の中で貧程つらいものはない」と世に言われますが、貧乏の苦しみはなかなかツライものがあります。そんな時に名利を目の前にちらつかされると、どんなことでも飛びつくのが人間の実相です。そして、少し脅されただけでいとも簡単に志を曲げて迎合する。名利の心にドップリ漬かり切っていると、後悔先に立たずの苦境は避けられません。
生半可な信念や付け焼き刃の学問教養では、名利の二益を前にするとあっけなく崩れてしまいます。そこを「脱却」してくことで、自己をどこどこまでも磨いていくのが、「名利の心を脱却すべし」という一節になります。つまり、孟子の言葉を借りるならば「真の大丈夫を目指しなさいよ」ということです。
「始末に困る輩」を目標にしよう!
西郷隆盛は、この『孟子』の一節を引き、このような「大丈夫」は「始末に困るもの」と述べています。それはそうでしょう。金品で懐柔することはできないし、追い詰めても節操を変えることはしないし、力で脅しつけても屈服しないのですから。それに続いて、「このような始末に困るものでなければ、大業を共に成し遂げることはできない」と明らかにしています。自己の修養・研鑽が十分に仕上がっているならば、どんな困難・難局にあってもブレることがありません。君臣一体となって突破していけるのです。
リーダーシップや組織マネジメントに、「公正無私」な「中庸の徳」を取り入れよう!
いずれにも偏ることがない「中庸の徳」に基づく組織運営は、長久に組織を保つうえでも大切なものになります。信賞必罰1つとっても、実情に基づかない極端なものは信頼を損ない、組織の勢いを削ぐことにつながることにもなるのです。
鈴木貫太郎の「奉公十則」は、学問に基づく帝王学が詰まったものになっています。その教えをビジネスや人生に取り入れ、役立ててみませんか?